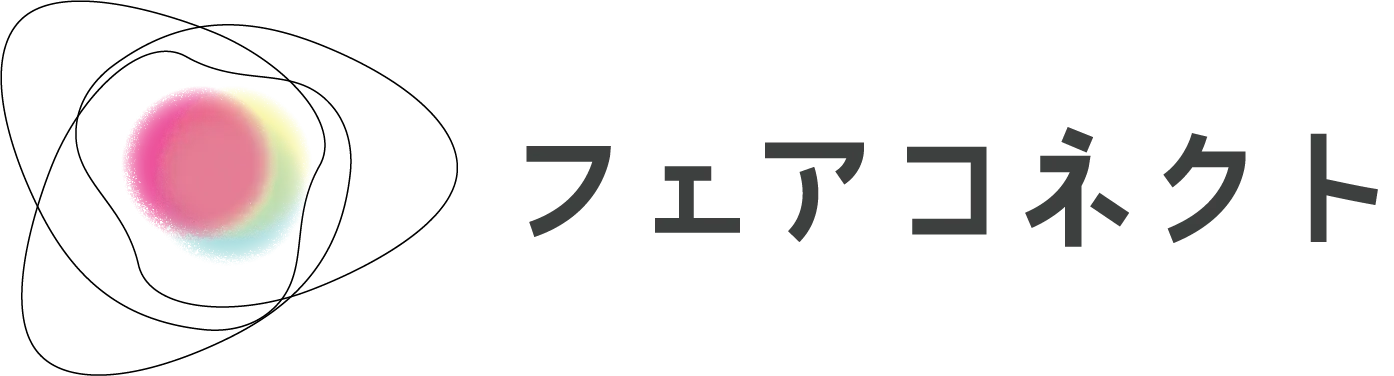障がい者雇用とは、身体・知的・精神のいずれかの障がいがある方が、企業や公的機関で働くことを指します。日本では「障害者雇用促進法」に基づき、一定の条件を満たす企業には障がい者を雇用する義務(法定雇用率)が課せられています。ここでは、障がい者雇用の仕組みや働く際のポイントについて詳しく説明します。
1. 障がい者雇用の制度と法律
① 障害者雇用促進法
障がいのある人が適切に働ける環境を整えるために、以下のような取り組みが求められています。
- 法定雇用率の設定
一定の従業員数以上の企業は、一定割合の障がい者を雇用しなければなりません。- 民間企業:2.3%(2024年4月から2.5%に引き上げ)
- 国や自治体などの公的機関:2.6%
- 都道府県の教育委員会:2.5%
- 障がい者雇用納付金制度
法定雇用率を達成できていない企業は、納付金を支払う義務があります。 - 合理的配慮の提供義務
障がいのある人が働きやすい環境を整えるために、企業は業務内容や労働環境の調整を行う必要があります。
2. 障がい者雇用の主な働き方
障がい者雇用には、いくつかの働き方があります。自分に合った雇用形態を選ぶことが大切です。
① 一般就労
- 障がい者枠ではなく、一般の求人で働く形態。
- 障がいの有無に関わらず、同じ条件で雇用される。
② 障がい者雇用枠(特例子会社を含む)
- 企業が障がい者のために用意する特別な雇用枠。
- 業務内容や職場環境が障がい特性に配慮されている。
- 「特例子会社」と呼ばれる、障がい者の雇用を推進するための専門企業も存在。
③ 就労継続支援(A型・B型)
- 一般企業で働くのが難しい人向けの支援付き就労制度。
- A型: 雇用契約を結び、最低賃金が保証される。
- B型: 雇用契約なし。工賃(給料のようなもの)は支払われるが、金額は低め。
④ 在宅就労(テレワーク)
- 通勤が難しい人向けに、自宅で仕事ができる制度を利用するケースも増加中。
3. 障がい者雇用での職種
障がいの種類や得意なことに応じて、さまざまな職種があります。
- デスクワーク系
- 事務(データ入力、書類整理、経理補助)
- コールセンター業務
- IT・プログラミング
- 軽作業系
- 工場でのライン作業
- 商品の梱包・仕分け
- 清掃業務
- クリエイティブ系
- デザイン(グラフィックデザイン、DTP)
- Web制作・動画編集
- 専門職系
- カウンセラー、福祉関係の仕事
- 資格を活かした業務(税理士、社労士など)
4. 障がい者雇用で働くメリットと課題
① メリット
- 配慮を受けながら働ける
体調や障がいの特性に合わせた働き方が可能。 - 安定した収入を得られる
障がい者雇用枠では、企業が長期的に雇用を維持することを前提としている場合が多い。 - サポートが充実している
企業の障がい者雇用支援制度や、公的機関(ハローワーク、障害者就業・生活支援センター)を利用できる。
② 課題
- 業務の選択肢が限られる
企業によっては、単純作業の仕事が中心となる場合がある。 - 給与が低めになる場合がある
一般雇用よりも賃金が低いことが多い。 - 昇進・キャリアアップの機会が少ない
一定のポジションにとどまるケースもあるため、長期的なキャリアプランを考える必要がある。
5. 障がい者雇用で働くためのポイント
① 就職活動の進め方
- 自分の障がい特性を理解する
- どのような配慮が必要か整理する。
- 診断書や障害者手帳の活用。
- ハローワークや支援機関を活用する
- 「障害者雇用専門の窓口」がある。
- 就労移行支援を利用すると、スキルアップしながら就職活動が可能。
- 企業の障がい者雇用実績を確認する
- 企業のホームページや口コミを調べる。
- 面接時に職場環境を確認する。
② 長く働くために大切なこと
- 体調管理をしっかりする
- 職場での相談窓口を活用する
- スキルアップを継続する
6. まとめ
障がい者雇用は、適切な環境で安心して働くことができる大切な制度です。自分に合った働き方を見つけるためには、制度を理解し、利用できる支援を積極的に活用することが重要です。就職活動の際には、企業の雇用実績や職場環境をよく調べ、自分の特性に合った仕事を選ぶようにしましょう。