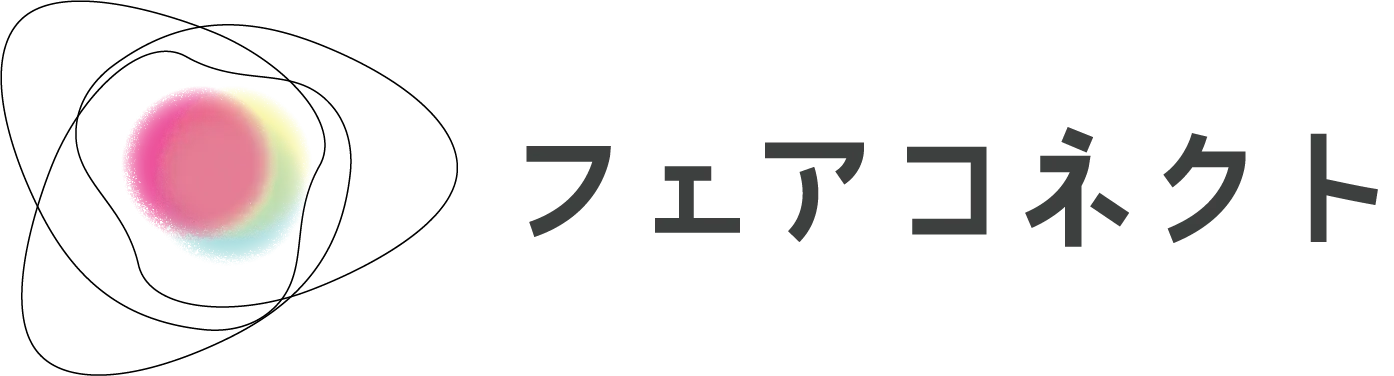企業・福祉・家族の連携がカギ
障がいのある方が就職を果たすことは、ゴールではなく「新たなスタート」です。
しかし実際には、「職場にうまくなじめない」「配慮が続かない」「体調を崩してしまった」などの理由から、
就職後すぐに離職してしまうケースも少なくありません。
こうした課題を乗り越え、安定して働き続けるために必要なのが「就労定着支援」です。
この記事では、企業・福祉・家族それぞれがどのように関わることで、
本人の“定着”を支えられるのかを考えていきます。
■ なぜ「定着」が難しいのか?
障がいのある方が職場に“定着”することが難しい背景には、以下のような要因があります。
- 職場の理解や配慮が十分でない
- 本人が困りごとを言い出せない
- 働き続ける体力・生活リズムが整っていない
- 仕事の内容と特性のミスマッチ
- 周囲との人間関係のストレス
このような問題は、本人だけの努力では解決できないものも多くあります。
だからこそ、周囲の「連携」と「支援」が不可欠なのです。
■ 企業の役割:柔軟な対応と、信頼関係の構築
企業にとっても、障がい者雇用は“共に働くパートナー”としての関わりが求められます。
たとえば…
- 仕事のマニュアルを分かりやすくする
- 無理のない業務量を調整する
- 毎朝の「ひと言声かけ」など、小さな安心を積み重ねる
- 困ったときに相談できる「窓口」や担当者を明確にする
重要なのは、“特別扱い”ではなく適切な理解と配慮です。
障がいのある方が安心して働ける職場環境づくりは、他の従業員にとっても優しい職場づくりにつながります。
■ 福祉の役割:職場と本人を「つなぐ支援者」
就労移行支援事業所や定着支援機関は、企業と本人の間に立ち、第三者として調整やアドバイスを行います。
具体的には…
- 定期的な職場訪問・面談による状況確認
- 本人が言いにくい悩みの“代弁”や伝達
- 企業への障がい理解のサポート
- 必要に応じて支援計画の見直し
本人がトラブルや困りごとを抱え込んでしまう前に、「早めに気づき、支える」ことが福祉の大切な役割です。
■ 家族の役割:毎日の安心の土台づくり
家族は、仕事の現場とは離れていても、本人の生活の基盤を支えています。
家族にできること:
- 就職後も、生活リズムや体調の変化に気を配る
- 働くことへの励ましや共感の言葉をかける
- 不安や愚痴を聞いてあげる「安心の受け皿」になる
- 必要に応じて、支援機関と情報共有する
「よく頑張ってるね」「無理しすぎてない?」
そんな一言が、働く本人にとって大きな支えになります。
■ 三者の“チーム”で、安定した就労へ
就労の「定着」は、企業・福祉・家族の三者がそれぞれの立場で支え合い、情報を共有することで実現します。
ときには、課題が見つかることもあるでしょう。
でも、それを責めるのではなく、「どうすれば一緒に乗り越えられるか?」と考えられる関係性が重要です。
■ まとめ:ゴールではなく、育んでいく「関係」
就労とは、単に仕事をすることではありません。
その人の人生にとって「役割」や「自信」につながる大切な機会です。
定着支援は、ただ長く働くためのサポートではなく、本人が安心して“自分らしく”働き続けられる環境を整える取り組みです。
企業・福祉・家族がチームとなって、障がいのある方の“働き続ける力”を育み、支えていきましょう。